
Top
Member
Works
Friends
BBS
Diary
Movies
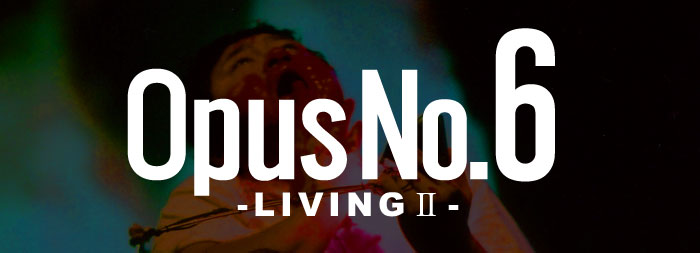
OM-2 「作品No.6」 - LIVING Ⅱ-
3.6Fri~.9Mon
複数の批評家からその年のベストワンと評された「作品No.4」-リビング-から出発した作品。
私たち個人や、社会が抱える問題をモチーフとして、私の<核>に迫ろうとする。
真に生きようとする人間の、それぞれのリビング。
|
■ 会場・日程 d-倉庫 |
 |
|
■ 料金
前売り Advance/¥2,800 当 日 Box office/¥3,300 学生割引 student discount(要学生証)/各¥500引き ■ チケット取り扱い
~上のページで予約後(要登録・無料)セブンイレブンですぐ発券
・簡単予約フォーム~予約のみで当日受付にてご清算される方はこちらからご予約下さい。 E-mail|info@om-2.net Tel|die pratze 03-3235-7990 (火曜定休 12:30~17:30) |
|
 |
■ OM-2 黄色舞伎團2として、真壁茂夫を中心に1987年に結成される。 以来、常に実験的、前衛的であり続け、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、北米などの海外でも高い評価を得ている。 最近では完全に台本を排除し、言葉によるテーマ、コンセプト、方法を取り去り、即興の練習を積み重ねることによって創られる、複数回行うことを前提としない一回性の作品創りをしている。 美的に優れたものを提示することでもなく、ことさら何かの行為を行うのでもなく、言葉による意味や解釈、分析を拒否し、ひたすら自己と闘い続ける。人間の「核(生きる根拠)」のみをさらけ出し、そこにこそ意義を見出そうとする。 |
|
架空の『リビング・ルーム』に立ち現れたのは、
目をそむけたくなるばかりの、私達の生のリアリティだった。 OM-2 『作品No.4-リビング-』 |
|
Composition & Direction : SHIGEO MAKABE ■ 出演|Performers 中井尋央|HIROO NAKAI 柴崎直子|NAOKO SHIBASAKI 丹生谷真由子|MAYUKO NYUNOYA 平澤晴花|HARUKA HIRASAWA 金原知輝|TOMOKI KIMPARA 大根田真人| MASATO ONEDA 吉澤啓太|KEITA YOSHIZAWA 岩井晶子|SHOKO IWAI 山口ゆりあ|YAMAGUCHI YURIA ほか・・・|and others 舞台美術/速水まりや、寺澤勇樹、五木田唯衣 舞台監督/長堀博士 舞台監督助手/田中新一 映像/藤野禎崇、赤瀬靖治 照明/三枝淳 音響/齋藤瑠美子 作曲/佐々木敦、他 小道具/池田包子 宣伝美術/小田善久 写真/田中英世、大久保由利子、Otto Muhlethaler 記録映像/船橋貞信、高橋弥生、四方隆夫 制作/村岡尚子 協力/ J・佐藤、田口博史、RAKUENOH+、 JAPAN NOW 実行委員会 (ロンドン: Bernard Deane Armstrong、 ワルシャワ: Imre Thormann, Paulina Marta Neukampf)、 R Production(菊池領子) |
 |
.gif) 助成/芸術文化振興基金 助成/芸術文化振興基金  企画・製作/Workom 企画・製作/Workom  協賛/die pratze 主催/OM-2 |
|
<OM-2 次回公演予告>
|
